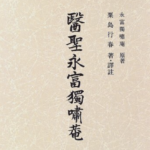未 病
素問の本文を読み進むと数ページで未病という言葉に出逢います。
養命酒のCMからすっかり有名な言葉になりましたが、この素問では『上医治未病也』との文で表現されています。
“未病”とは、健康と病気の間、あるいは病気になる前の状態のことと理解している方が多いと思います。
故粟島先生、そして島添先生も、『そうではない』と仰います。
以前からそう聞いてはいましたが、何処がどう違うのか曖昧でした。
今回、少し腑に落ちました。
前回、全ての物事は
太易=未だ氣をあらわさず 太初=氣の始まりなり 太始=形の始まりなり 太素=質の始まりなり
と展開していくと記しました。未病とは健康と病気の間の状態ではなく、病気が形になって現れる前の太初で、種のようなもの。
漠然とした状態ではなく、既に存在する具体的なもの。
例えば、『腎臓に未病があるから治療しましょう』というように、既に治療の対象となるものなのだと理解しました。
中医学には、診断手法として“望診”触診”舌診”脈診”などがあります。これらは、この未病を発見するための手法なのでしょう。
未病を発見し、治療できる医師が上医(上工)と呼ばれ、優れた医師なのです。
既に形として現れている病を治療するのは中医(中工)で、普通の医師です。
未病とは、病気になる前の状態ではなく、病気の始まり、そう、既に病み始めているのです。
Y.Izumi