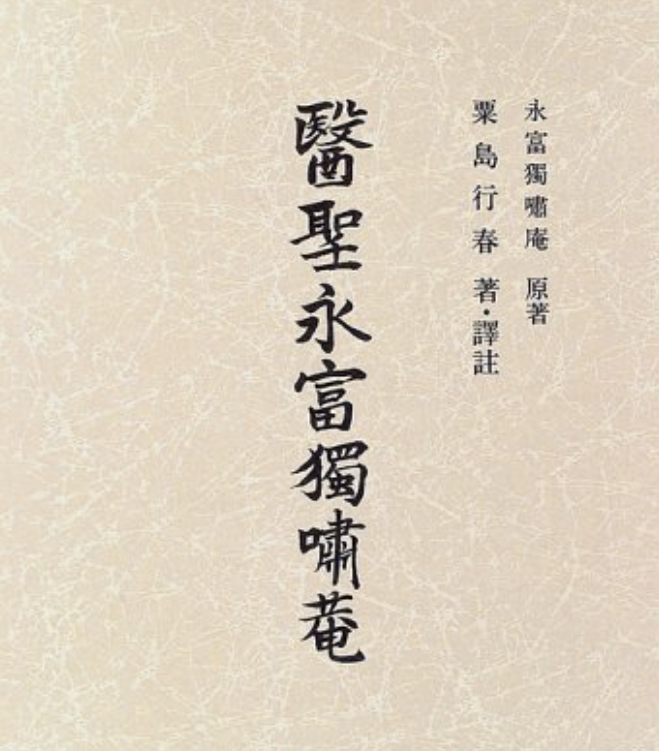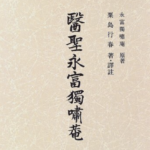粟島行春著・訳註 「醫聖 永富獨嘯庵」(ながとみ どくしょうあん)(2)
前回からの続きです。
船の中で鳳介は果てしない古代中国の聖賢について語り、船頭たちはこのおそるべき少年の話に感動しました。そこで、大阪に着いてから、難波一の大親分や京都一の金持ちを紹介します。しかし、鳳介が探していたのは学問の師であり、残念ながら探し当てることができずに宇部村に帰ってきます。
鳳介は12歳の時、心臓を病みます。かなりの重症で、全身青く浮腫み、歩行もままらない状態になりました。父治左衛門は、永富友庵の医局に連れて行きます。彼の医学はいわゆる後世方です。当時の京都は、田代三喜が持ち帰った後世方が全盛の時代でした。友庵の治療によって少しずつではあるものの良くなっていきます。そして、友庵の手伝いもできるようになってきました。ただ、鳳介が受けた後世方の医術は、温補を主とした治療法であったために、一時的に小康を得ても、完全に病気を払拭できませんでした。結果的に、この病気を生涯背負うことになってしまいます。古方の医学者として大を成す鳳介が、後世方の治療を受けたのは皮肉とも言えるかもしれません。
ところで、鳳介の才能に惚れ込んだ友庵は、治左衛門にお願いして婿養子にします。こうして、永富家を継ぐことになったのです。永富家に入ってしばらくして、学ぶべきこともなくなります。友庵の配慮もあり、萩の侍医の門に入ることになります。鳳介12歳の時です。名も朝陽と称します。しかし、ここでもあっという間に全てを学び、悶々とした日々を送ることになります。そんな折、ふとしたきっかけで儒学者の山縣周南に出会い、その門下になります。周南も朝陽の才能に気づき、「わが徂徠学派を後世に存在せしむるは、一人朝陽あるのみ」と言わしめます。そんな朝陽が、医家たるべきか儒家たるべきかを迷い、その悩みを江戸の医家にぶつけてみようと思うようになります。そして14歳の時に江戸に旅立ちます。その時は、師・周南もに見送っています。
しかし、江戸の医者は、ひとえに利欲に迷い、へつらい、高位高官に取り入れるような者ばかり多く、医者を厭う気が強くなり、儒家に目が向いてくるようになります。しかし、安達寿軒という人物が訪ねてきて、本物の医者である香川秀庵や山脇東洋になぜ会わぬかと言います。そして東洋の門下に入ることになります。朝陽は「その言、いまだ終わらざるに下上がりて降らず、汗流れて背にあまねし。生涯の趣向はじめて定まる」と東洋と会った時の様子を記しています。門下に入って間もなく、「東洋の門下に永富朝陽あり」と、その名は次第に知れわたっていきます。すでに有名になっていた吉益東洞も「隠全たる、一敵国の如しとは、それ永富の子か。吾れ死せば、まさにこの人を以って海内医流の完冕(かんべん)となすべき」と嘆じるほどでした。
当時の東洋の医学は、「汗」・「下」・「和」の方は完璧に備わっていたと言えます。そこで朝陽は、吐方の研究をしている奥村良竹から学んでくるように命を受けます。そして、彼から半年ほど学んで京に戻ります。自分が学んだ吐方を師に授けたので、山脇東洋は、汗・吐・下・和の4方をことごとく備えることになったのです。
人体解剖書である「蔵志」の原稿も書き上がり、一息をついた山脇東洋。茶室を新たに建立し、貴重な軸物、高価な茶器を蔵し、侘び寂びの趣向に、その時間を注ぎ込むようになります。門下への教育も怠りがちになり、朝陽は面白くない気持ちを抱き始めます。ある日、東洋の茶室に入り、大切にしていた茶器を持ち出し、大きな踏み石にめがけて打ちつけ、木っ端微塵に壊してしまいます。帰ってきた東洋は、その有り様を眺めるも、一言も声をかけません。「粗相をいたし、申し訳ありませぬ。」と平伏する朝陽。東洋は無言のまま茶室に入ります。お互いに見えないところで坐すこと一時半。やがて、茶室の襖が開き、東洋は静かな口調で言います。「余が悪かった。許せよ。」酷く叱責され、必ず処分されると覚悟を決めていた朝陽は、意外の言にハラハラと涙を流します。東洋の広い心で、何事もなく収まったものの、師に詫びさせた弟子としては、踏みとどまることはできないと考えます。必ず大恩に報いることを誓い、数年間のお暇をいただきたいと申し出ます。必死に止める東洋に、「では3年間のお暇を」と乞いますが、東洋は「寂しいぞ。2年にしろ。」ということで、東洋のもとをしばし去ることになるのです。
・・・さらに次号[3]へ続きます。(ここを押してくだい。続きへ飛びます)
「薬事日報 電子版」掲載記事より